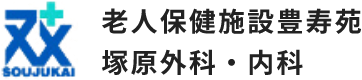Poison & Medicine ブログ 毒と薬
2014.12.18
豊寿苑
音楽とアート
認知症と音楽療法〜映画『パーソナル・ソング』を観て【1】

映画『パーソナル・ソング』から
ある日、東京の知り合いの編集者から
「塚原さんにぴったりの映画が公開されるので映画評を書いていただけませんか?」
というメールをいただきました。
それは『パーソナル・ソング』という認知症と音楽について描いたアメリカのドキュメンタリー映画でした。
たまたま、『レナードの朝』の原作で知られるアメリカの脳神経科医オリヴァー・サックスの『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』(ハヤカワ・ノン・フィクション文庫)を読み終えたばかりだったこともあり、快く引き受けました。
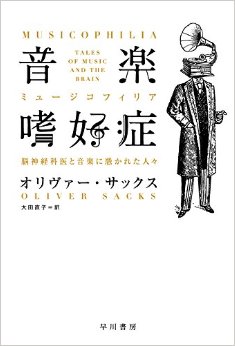
オリヴァー・サックス『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』ハヤカワ・ノン・フィクション文庫
数日後、編集部からサンプルDVDが届けられました。〆切が迫っているのでさっそく観ようと思ったところ、「どうせならスタッフにも観てもらおう」と緊急に施設で上映会を開くことにしました。
急な呼びかけだったにもかかわらず、上映会には入所・通所担当の介護スタッフはじめ、相談員、ケアマネージャーなど、15人ほどが集まりました。
マイケル・ロサト=ベネット監督によるこのドキュメンタリー映画は、ダン・コーエンという以前IT関連の仕事をしていたソーシャル・ワーカーが、認知症、多発性硬化症、双極性障害といった疾患により病院、介護施設、あるいは在宅で療養している人びとを訪ね、それぞれの思い出の音楽(パーソナル・ソング)を探り当てて、かれらの閉ざされた心に光を灯していく物語です。
映画の冒頭、こんな印象的なシーンがあります。
介護施設に入所して10年になる94歳の黒人男性ヘンリーは重い認知症。1日中、車イスで一人ポツンと無表情にうつむいたまま過ごしています。面会に訪れた娘の名まえさえ覚えていません。
ダン・コーエンは、ヘンリーが若い頃、熱心に教会へ通っていたという話を聞いて、彼にヘッドフォンでゴスペルの名曲’Goin’ Up Yonder’ を聞かせます。
すると、ヘンリーは突然目を輝かせ、身体を揺らしながら歌い出します。そして、若い頃の記憶や思考や気分などが次々とよみがえってきて、かれは生き生きとした表情で語り始めます。
ちなみに、ヘンリーのお気に入りは、30〜40年代に大人気だった「ミニー・ザ・ムーチャー (Minnie The Moocher) 」で知られる〝ジャイヴの王様〟キャブ・キャロウェイでした。
私もキャブ・キャロウェイは大好きです。
映画ではキャブが自らのビッグバンド率いてハイテンションで歌い踊るシーンがはさまれ、興奮した口調でキャブのことを語るヘンリーのうれしそうな表情との相乗効果によって、つい表情が緩んでしまいました。

キャブ・キャロウェイと彼の楽団
映画にはオリヴァー・サックス医師も出ています。前述の『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』で、彼は音楽と脳の関係について次のように説明しています。
音楽の認識は、人間の脳の1個所でおこなわれるのではなく、脳の全体に散らばっているさまざまな部位のネットワークからなっています。つまり、音質、音色、音程、メロディ、和音、リズムを感じとる脳の部位がそれぞれに分かれていて、これらを頭のなかで統合して音楽として認識するというのです。
さらにこの構造的な認識に、感情的な反応が加わって、運動をもうながします。音楽は脳の広い範囲を刺激するばかりでなく、感情を呼び起こし、身体運動をもたらすというのです。ヘンリーはそのもっともわかりやすいケースといえるでしょう。
サックス医師は、映画の中で音楽は認知症によるダメージを比較的受けにくいともいっています。
これは、音楽として認識する脳の部位が各所に散っているおかげでリスクも分散されるというふうに理解すべきなのでしょうか?
脳は通常、優位な方の脳半球がもう一方の脳半球の働きを抑え込んでいます。それが、たとえば脳卒中によって優位脳半球の広い部位が損なわれたりすると、抑制されていた脳の機能が解放されることが起こるようです。
音楽が認知症に効果があるというのは、このように解放された脳の部位を刺激し活性化させるためではないかと私は考えます。
音楽療法というと、当施設でもそうですが、集団で懐かしい歌をうたったり楽器を演奏したりするのが一般的です。ダン・コーエンの音楽療法がユニークなのは、iPodを使って一人ひとりにヘッドフォンで音楽を提供している点です。
私もランニングや筋トレのときiPodをしています。これによってざわついた外の環境からある程度、情報遮断ができ、運動に集中できるだけでなく内省が高まってイマジネーションがわいてきます。ダンがやったのはこれとおなじ原理かと思います。
(続く)